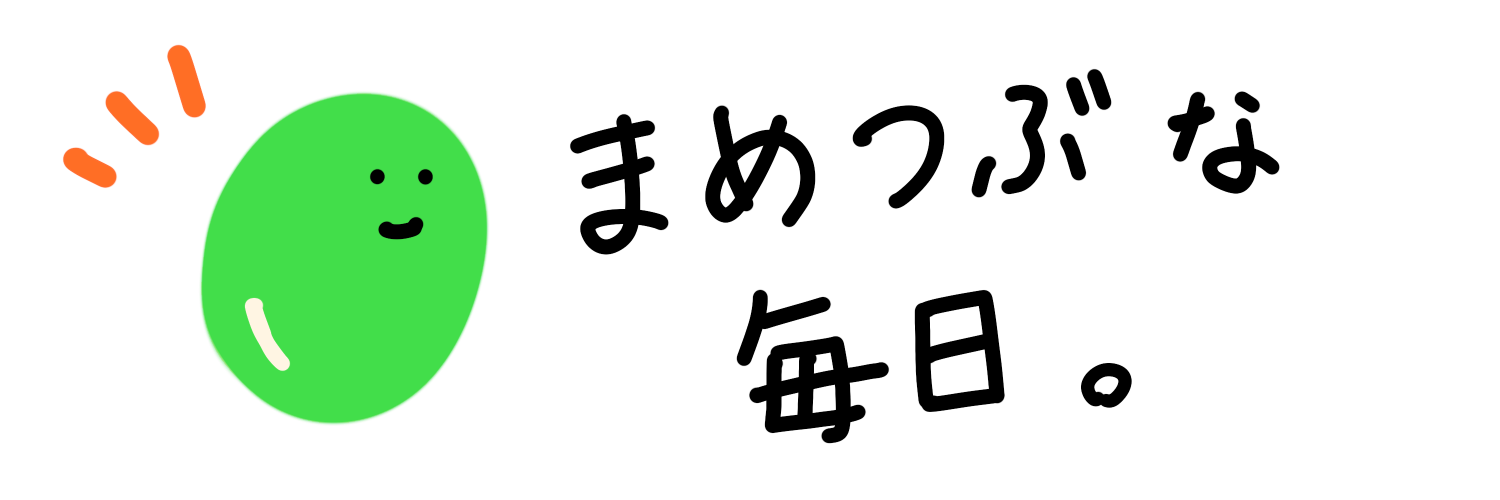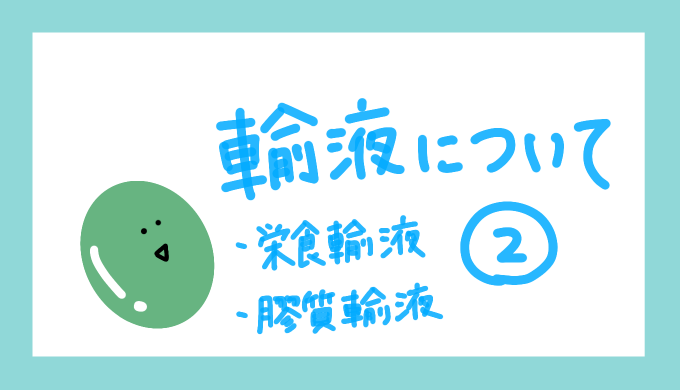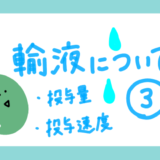こんにちはー!おまめです!
今回の勉強ノートは前々回から始まりました輸液についての続編です!
一応今回の「輸液について②」で一区切りにしようかなと思います。
一応前回と前々回の記事を貼っておきますね!
まだご覧になってないない方はどうぞこちらからお読みください!
この記事の前に読むと流れがわかるので、わかりやすいと思います!
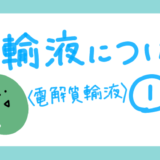 【看護師の勉強ノート】輸液について①
【看護師の勉強ノート】輸液について①
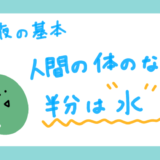 【輸液の基本】人間の体のなか、半分は水
【輸液の基本】人間の体のなか、半分は水
あと、アイキャッチ画像を固定化するって言ってたんですけど、全然あってなくて辞めました笑笑
また書き直してから考えます。笑
では、さっそく行きましょう!
今回は、栄養輸液と膠質液についてを解説していこうと思います!!
目次
栄養輸液というのは主に、高カロリー輸液と、アミノ酸輸液、脂肪乳剤などがあります。
どれも、臨床では患者さんの不足した栄養を補う役割をしています。
一つずつ解説していこうと思います👇
高カロリー輸液
臨高カロリー輸液は通称TPN(total parenteral nutrition)と呼ばれていて、
完全静脈栄養法という意味です。
必要なエネルギー、電解質、栄養素を経静脈的に必要分量を投与する栄養法です。
代表的な製剤の名前は、ネオパレンとか、エルネオパ、フルカリック、ハイカリックなどです!
TPNは末梢静脈(前腕とか上腕とか脚)からではなくて、中心静脈に留置したカテーテル(CVカテーテル)を介して投与するというルールがあります。
これは、末梢静脈からだと静脈炎を起こしやすいからです。中心静脈は血管が太いので、血液がたくさん流れており、濃度の高い高カロリー輸液でも血液で薄まり、血管に影響が出にくいとされているためです。
高カロリー輸液の注意点は、急に投与を開始したり、急に投与を中止することはしない!ってことです。
通常は、糖の濃度が低い1号液から開始し、その後2号液に切り替えていくのがスタンダードです。
急激な血糖上昇による高血糖や肝機能障害に注意が必要です!
ネオパレンについては、結構前に記事にも書いているので、そちらも参考にしていただけるといいかと思います!
 【看護師4年目】ネオパレンと献血ヴェノグロブリンについて
【看護師4年目】ネオパレンと献血ヴェノグロブリンについて
アミノ酸輸液
アミノ酸輸液は、名前の通りでアミノ酸の補充とバランスを整える輸液です。
病態によって適正組成アミノ酸製剤があります!(腎障害、肝不全、総合アミノ酸、小児用など)
TPNの普及に伴って、日本ではタンパク源として用いられることが多いです!
代表的な製品はビーフリード、アミゼットとかです。
ビーフリードは、ブドウ糖と電解質、アミノ酸加えてビタミンB1が含まれているのが特徴で、血中濃度を維持する効果があります!
アミゼットは侵襲時用アミノ酸製剤という種類に区分されている製剤です。ちなみにネオパレンとかもここの分類に入ってました!
私のイメージでは、ご飯が食べれなくなった患者さんに1番最初にする点滴って感じです。
まず末梢からビーフリードなどのアミノ酸製剤をいって、それでもだめなら胃管入れるかCV入れるか(中心静脈栄養)って感じ・・・
脂肪乳剤
これは私のいた病棟ではごくたまーにいってたくらいですね。
白ーい輸液製剤です。笑
脂肪乳剤の投与の目的は効率よくエネルギーの補給と必要脂肪酸の供給することです。
脂質は9kcal/gで糖質やタンパク質と比べて2倍以上の高率よいエネルギーを有します!!
エネルギー源が糖質だけだと、高血糖やインスリン分泌に伴う脂肪合成が亢進して脂肪肝になっちゃうのです・・・
脂肪乳剤はこれらの副作用を低減するために投与するのです!
代表的な脂肪乳剤はイントラリポスです!
必須脂肪酸を含まないTPNを数週間投与をすると、必須脂肪酸欠乏症が発症すると言われています!
主な症状は皮膚の乾燥、脱毛、脂肪肝、免疫不全、血小板減少などです。
脂肪乳剤は、投与速度が速すぎると脂質のリポ蛋白化が間に合わず、消化できないで血中に取り残される。
血中脂質濃度が上がって脂質異常症になる危険があるので、0.1g/㎏/hの速度での投与が鉄則!
(体重50㎏の人なら4時間かけて投与する!)
膠質とは、アルブミンなどの分子量の大きい粒子のことをいいます。
反対に晶質とは、ナトリウムなどの分子量の小さな粒子を含むものをいいます。
膠質液はアルブミンの膠質浸透圧によって、血管内にとどまりやすいことから、血漿増量剤とも呼ばれています!
等張性・低張性電解質輸液は、晶質液になる!
アルブミンの分子量が66000に対して、ナトリウムの分子量は23!!(すくな!!笑)
代表的な膠質液は5%アルブミン液や25%アルブミン液です。
5%アルブミン液は血管内にとどまる役割が大きいですが、25%アルブミン液は、間質や細胞内からも水を引っ張ってくることができるほど浸透圧が高いです!!
よく脳神経外科で使用する「デキストランL」という輸液製剤も、でんぷん製剤という種類で膠質液の仲間です!
デキストランLも浸透圧が高く、血管内にとどまって血漿増量剤の役割をします!
この膠質液は、血漿増量剤とも呼ばれていることからも、主に出血性ショックの時なんかに使用されます。
あとは、血管内脱水がひどい時とかですかね・・・
今日は栄養輸液と膠質液について書いていきました!
お役に立てる内容でしたでしょうか?わかりにくいところなどあればお問い合わせホームに書いていただけると嬉しいです!
栄養輸液は、患者さんがご飯の食べる量が少なかったり、意識状態的に食べれなくなってしまったときなどに開始する輸液です。
臨床でも見かけることが多い製剤なので、覚えておくと絶対にいいです!!
膠質液に関しては、イントラリポスなんかはたまにしか見かけないのですが、デキストランLとかは、脳外にいると脳梗塞の発症まもない患者さんとかによく使用されていました。
浸透圧って難しそうでいやな言葉だって思っていましたが、覚えてしまうと割と簡単です!
輸液の基本ともいえる考え方なので、とっても重要だということがわかりました!
これで一旦輸液についての記事はしばらくお休みです!
次回もお楽しみ!
おわり。